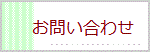リレーエッセー 第81弾
本学 名誉教授 佐藤 晴彦(修2C)
はじめまして。
私は、本年三月まで、神戸市外国語大学中国学科で教員をしていました。 1982年に赴任しましたので、31年間、母校で教鞭を執っていたことになります。 四月以降は、少しでも母校のお役に立てるならと思い、同窓会で常任理事となりました。 新米ですので、どうぞよろしくお願いします。
敦煌、西安再訪
ひょんなことがきっかけとなり、毎年夏休み、10名前後の友人たちと中国旅行に出かけている。 最初に行ったのが、2004年だったから、もう丸10年になる。 これまで甘粛(敦煌)、陝西(西安)、山東(曲阜、青島)、三峡下り、九寨溝、海南島、東北(ハルピン、長春、瀋陽)、新疆(ウルムチ、カシュガル、クチャ)、江西(盧山、東林寺、景徳鎮、ブ源)などを訪れている。 それぞれが印象深いところだった。
一回目の2004年は敦煌と西安だった。 それというのも、この会の中心メンバーがかつて入矢義高先生(京都大学教授。大変な硯学として夙に名を馳せられた先生であったが、とりわけ敦煌文書の研究、禅の語録の研究では大きな足跡を残された。 本学で教鞭を執られていた太田辰夫先生とは互いに認め合う間柄であった。1998年逝去。) の研究会という席で知り合った関係で、暗黙のうちに、「一番初めに行きたいところは、やはり敦煌やなあ。」ということになり、敦煌、西安行きが決まった。 入矢義高先生のもとで10年、20年と敦煌文書を読んできたから、どうしてもこの足で敦煌の地を踏みたかったし、この目で、敦煌の街を見たかったからである。 敦煌へ行けば、当然、周秦漢隋唐を通じて都であった長安(現在の西安)に行ってみたいというのも、当然のなりゆきであった。 初めての敦煌の地に降り立った時は、長年夢見て来ただけに、感動モノだった。
今回、敦煌西安再訪となったわけだが、10年前にも行ったところもあれば、今回初めて行ったところもある。 そうした訪問先印象の一斑を誌してみたい。
溢れる観光客今年、敦煌、西安を再訪して一番驚いたのが観光客の多さだった。 莫高窟しかり、鳴沙山しかり、月牙泉しかり、兵馬俑しかりというありさまで、至るところ、人、人,人というイメージしか残らなかった。 特に人が多かったのが兵馬俑。 10年前に行った時は、人が多くなく、涼しい中でゆったりと見ることができたが、今年はさながら満員電車状態。 人いきれでむんむんしており、クーラーがあっても人が多いからであろう、十分効いていなかったため、汗だくのありさま。
(1)西安編
1.秦の兵馬俑

兵馬俑の入場料は一人90元(但し、1月〜2月のオフシーズンは65元)。 現行の換算率は、1元=17円なので、1541円になる。 あれだけの古代遺産を見学できるのであるから、わたしたちの感覚からすれば、「安い」と思うが、さて中国人の立場からすれば、どうだろう? 北京の平均月収は35500円(但し2007年度)と言われているので、その月収を考慮に入れれば、かなり高いという感覚ではないだろうか。 それでも多くの観光客であふれているのだから、それだけ関心度が高いのであろう。
2.兵馬俑の発見者

楊継徳さんは、兵馬俑の写真集を買ってくれた観光客にサインするため、こうして待機しているらしい。 上の幟には"秦俑発現人楊継徳先生簽名售書"(秦兵馬俑発見者楊継徳氏サイン入り書籍販売)と書かれてある。
兵馬俑は1974年に発見されたというから、発見から40年経ったということになる。発見者は9人いたらしいが、発見からすでに40年経っているわけだから、すでに5名の方が亡くなり、現在でもご健在なのは4名らしく、楊継徳さんはそのうちの一人。
これだけの遺跡を発見されたのであるから、発見の功績たるや一言で言い表すことができないほど、偉大な発見だったのだが、その結果、こうして毎日、人寄せパンダのような「仕事」をさせられるとは、ご本人は予想すらしなかったのではないだろうか。 見ていて何だか気の毒になってきた。 本人の心境を推し量れば、「こんなふうになるのなら、発見するのじゃなかった。」と思ったりしているのじゃないだろうか。

楊継徳さんは、毎日こうして会場にいるらしいが、観光客がフラッシュをたくため眼が悪くなり、普段はフラッシュを避けるため、こうして眼を隠していると聞いた。 「気の毒に」と思う気持ちがさらに強くなってきた。
3.西安のギョーザ

西安と聞いてすぐ思い出されるのは、さまざまな文物遺産であろうが、食べ物となれば、恐らくギョーザであろう。 10年前に行った時、スケジュールの中に「ギョーザパーティ」という項目があり、「何だろう?」と思っていた。 恥ずかしながら10年前には西安ではギョーザが有名な食べ物とは知らなかった。 ギョーザパーティと銘打つだけあって、ありとあらゆるギョーザが出て来た。聞くところではギョーザの種類は300種にも達するという。 写真で見られる通り、種類も豊富だが、色彩的にも実に鮮やかである。
4.西安の城壁
10年前は華清池へ行ったが、西安の城壁には上らなかった。 今回は城壁に上る機会に恵まれ、「バスが二台通れる城壁」という噂を聞いていたものの、どれだけ大きなものか、全く想像できなかった。いざ上がってみると度肝を抜かれた。 今年の1月に放送されたNHKBSプレミアム「古代中国 よみがえる英雄伝説▽始皇帝と乱世の名臣たち〜春秋戦国 天下統一への道〜」という番組で、レポーターの中井貴一氏が西安の城壁に登るなり、思わず「デカッ!」と口走ったが、実際この眼で見た時、全く同じ反応をしてしまった自分に気づき、苦笑いしてしまった。 まさに"百聞不如一見"(百聞は一見に如かず)の諺通りで、その広さには圧倒されてしまった。

西安の城壁は、北が4262m、南が4256m、東が2886m、西が2706mあるというから、全部でおよそ14kmになる。 高さは12m、幅は下が18m、上は15mあるらしい。 城壁の上でカートが走っているが、さすがにバスは走っていない。 時間があれば散歩を楽しむのもいいが、わたしたちはそんな余裕がなかったので、カートに乗って見物した。 貸し自転車もあるので、時間的に余裕があれば、自転車で巡るのも一興だろう。
(2)敦煌編
1.莫高窟

莫高窟には492の窟があると言われている。 "千佛堂"とも言われていたように、仏教遺跡であり、石刻や絵画、塑像、仏典などが豊富にあり、しかも1900年に手つかずの状態で発見された。 その発見をしたのが、当時この地にやってきた王円禄という道士で、彼はこの洞窟に住みつき、掃除をしたり、本の書写をしているうち、偶然第17窟を発見したという。 ただ王道士はそれらの資料の貴重さが分からず、二束三文で売ってしまったらしい。 1907年にはイギリスの探検家スタインが1万件を、1908年にはフランスの探検家ぺリオが5千件を持って行ってしまったとされている。 浄土真宗本願寺派の大谷光瑞を中心とする探検隊の第三次探検で、橘瑞超、野村栄三郎が敦煌に行き、敦煌文書を将来してきたのも、1908年、1909年の頃であった。 将来された文物、文書の多くは、龍谷大学が収蔵していると聞いている。
1911年が辛亥革命の年だから、1900年頃といえば、中国は混乱の時期であったため、こうした貴重な文化遺産が海外に流出してしまった。 中華人民共和国になってから、敦煌文書の文献目録が編纂されたが、その書名を『敦煌劫余録』という。 "劫"は「略奪する、奪い取る」ということなので、「外国人が貴重な文献の数々を奪い去った後の残りモノの記録」というなんともすさまじい命名法である。 当時の研究者たちの無念のほどを示すにあまりある。
2.月牙泉

月牙泉は古く、"渥ワ池"、"沙井"、"薬泉"などと呼ばれていたという。 漢代の頃から「敦煌八景」の一つに数えられるほど美しいところであった。 "月牙泉"と呼ばれるようになったのは、清代以降らしい。 "月牙"というのは、「三日月」のことを指すので、泉の形状を三日月に擬えたのだろう。 まさに砂漠のオアシスという感じがする泉である。
この写真は、砂丘を少し登って撮った。 10年前に来た時はなかったが、今は新たにワイヤーに板を取り付けた階段状のものが取りつけられ、砂丘を上がっていくのが、かなり楽になっていた。 それでも砂丘を登り切るのは、年寄りにとってかなりきつい「修行」で、わたしは途中で諦め降りて来た。
因みに月牙泉は、1960年頃では、水深が4m〜5m、一番深いところなら7.5mもあったらしい。 しかし、だんだん浅くなり、1990年代になると泉の面積も狭くなり、平均水深は0.9m、一番深いところでも1.3mしかないという。 2008年頃から応急の水利事業を行い、平均水位は30cmほど上昇したらしい。
3.鳴沙山

この写真を見れば、筆者と同年代の人たちが即座に連想されるのは、恐らく、「月の砂漠を、はるばると…♪」という童謡の一節ではなかろうか。 写真はむろん昼間に撮ったものなので、あいにく、「月の砂漠」となってはいないが、月が一輪浮かんでおれば、まさに「月の砂漠」そのものの光景である。 しかし、注意して写真の手前をご覧いただきたい。 手前に白いものが映っているが、何かお分かりだろうか。 そう、コンクリートで造られた歩道なのである。 10年前に鳴沙山を訪れた時は、こういうものはなかった。 筆者はこの光景を見た途端、"殺風景"という中国語を思い出した。 現代日本語の「殺風景」は、「景色などが、単調で趣のないこと。」(『大辞林』)というのが主たる語義であるが、中国語の原義は、文字通り「風景を殺す」→「景色が台無しになる」「興ざめ」という意味で、現在でもそのような意味で使われるのが一般的であり、日本語と若干ニュアンスが異なっている。
晩唐の詩人・李商隠に『義山雑ツァン』という面白い本があるが、そこで"シャ風景(=殺風景)"という語を取り上げ、どういうものが"殺風景"になるかという例を挙げている。 例えば、"月下把火"(月下のタイマツ)、"背山起樓"(山を背に建物を建てる)、"花下晒褌"(花の下で褌を干す)という類が、"殺風景"なものとして挙げられている。 筆者はこれらの"殺風景"に、「砂漠のコンクリート歩道」を加えたい気に駆られた。

上の写真をご覧いただきたい。 映っている人たちの足にみんなオレンジ色の何かを履いているのが見える。 鳴沙山は有名な砂漠地であるから、普通の靴では砂が靴の中に入り、見学の後で取ろうと思っても、粒子が細かいだけに、なかなか完全には除去し難いのである。 だからこういうサービスができたのであろうが、これも10年前にはなかった。 (サービスと言っても有料で、確か一人あたり15元だったと記憶する。)
観光客の増加にともない、アクセスが便利になったり、いろいろなサービスが生まれることは、自然のなりゆきかも知れないし、それ自体は大変結構なこととだ。 例えば「靴カバー」のようなものは、多少お金を徴収するにしても、非常に有用だと思う。 それにオレンジ色というのが、突き抜けるような空の青さとあいまっていいコントラストを示しており、色彩の選択としてもなかなかいいと思う。 しかし、コンクリートの歩道は如何なものであろう。 確かに歩きやすいかも知れないが、その分、千年、二千年あるいは数千年と継承されてきた文物に対し、まさに"殺風景"なことをしてはいないだろうか。 「文物の保護」は必ず継承していかなければならない。これだけ観光客が増加してきた現状ではとりわけ重要だと思う。 そうでなければ、文物そのものが痛手を被るであろう。 ただ、その方法に関して、「こういう方向性でいいのだろうか?」という若干の疑問を感じた次第である。