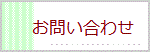リレーエッセー 第119弾
故・赤松光雄先生追悼エッセイ
一周忌に当たり恩師を偲んで
ボストン・レッド・ソックスの真実
H・ブライアント著『シャットアウト』(2002) を読む
近藤 馨(学24EA)
2021年シーズン合衆国のメジャー・リーグ球界は、ロサンジェルス・エンゼルスの大谷翔平の大活躍で沸きに沸いた。それはおそらく、およそ100年前にボストン・レッド・ソックス及びニューヨーク・ヤンキースで活躍した「野球の神様」ベーブ・ルースを凌ぐ勢いだった。いわゆる「投・打の二刀流」で、投げては9勝を挙げ、打っては46本塁打を放つ快挙が認められ「年間最優秀選手」に選出されたことでも判る。まだ27歳の伸び盛りの若者の一挙手一投足は、東京2020オリンピックで野球日本代表の「侍ジャパン」が、37年ぶりに悲願の金メダルを獲得した時以上に注目されたものである。
1964年の日本人メジャー・リーガー「第1号」村上雅則(当時南海ホークス所属、サンフランシスコ・ジャイアンツに入団)はさておき、95年の野茂英雄(近鉄バッファローズからロサンジェルス・ドジャーズに入団)以来、数多くの日本人が海を渡りメジャー・リーガーとして活躍している。中でも84年間破られることのなかったジョージ・シスラーの、シーズン最多安打記録を更新した「イチロー」こと鈴木一朗(オリックス・ブルーウェーブからシアトル・マリナーズ)の存在感は、引退後の今もなお健在だ。日本プロ野球界では、メジャー・リーグを経験した日本人選手が一軍監督に就任するようにもなっている(2018年シーズンより千葉ロッテ・マリーンズの井口資仁が第1号。福岡ダイエー・ホークスからシカゴ・ホワイトソックス)。第2号が、2021年シーズンを制覇した東京ヤクルト・スワローズの高津臣吾(ヤクルトからシカゴ・ホワイトソックスに入団)だ。就任1年目には最下位に終わったチームを、翌シーズン「日本一」に成長させた手腕には脱帽させられた。 そして2022年シーズンの開幕が間近だが、また一人の元メジャー・リーガーが「ビッグ・ボス」として日本球界への復帰を果たし話題となっている(新庄剛志。 阪神タイガースよりニューヨーク・メッツ)。2013年ドラフト会議で大谷翔平を引き当てた北海道日本ハム・ファイターズの監督・栗山英樹の後任に就任した。大谷が海を渡ってメジャー球界入りしたのは2018年だから、昨シーズンの大活躍は3年目の快挙だった。2022年シーズンは、果たしてどんな活躍を見せてくれるであろう。
かつての日本人プロ野球選手にとって、合衆国メジャー・リーグは夢のまた夢の存在だった。メジャー球界においても、まさか日本人選手が参入して来るとは夢にも思わなかっただろう。いや、すでに「自由と平等」を標榜して強大な多民族国家になっていた合衆国である。メジャー球界を目指していたのは、なにも日本人だけではなかった。だが、かつて奴隷制度で国家が大きく揺れた国である。第二次大戦後まもなくのことながら、メジャー球界では相変わらず「カラー・ライン」という人種の壁が厚く立ち塞がっていた。メジャー機構は白人のためのものであり、非白人すなわち有色人種が参入できる処ではなかったのだ。南部においては、白人専用と有色人用の客車やバスが走っていたり、公立学校及びレストランを始めあらゆる公共施設ではそれぞれ利用できる場所の制限があった。その不平等な扱いに業を煮やした若き黒人牧師が抗議運動に乗り出したのが、50年代から60年代のことである。
そんな時代背景の中、1947年のジャッキー・ロビンソンがブルックリン・ドジャーズに参入したことで、ようやくその「カラー・ライン」に風穴が開いた。それまでメジャー・リーグとは別物の、「ニグロ・リーグ」でしかプレーを許されなかった有能な選手たちがにわかに脚光を浴びるようになった。だが、最後の最後まで有色人プレーヤーを拒否しようとしたチームがあった。アメリカン・リーグの古豪ボストン・レッド・ソックスだ。
レッド・ソックスと言えば、合衆国メジャー球界でアメリカン・リーグ創設時からの古豪球団だ。創設当時には、後に歴代最多の通算511勝を挙げるサイ・ヤングが在籍していた。1910年代には、あのベーブ・ルースが投打の二刀流で、ワールド・シリーズ制覇の原動力として活躍している。打率 .406を記録した40年代の史上最高の左翼手テッド・ウィリアムズや、20世紀末のロジャー・クレメンスやペドロ・マルティネスの快投ぶり、そして松坂大輔や上原浩治の名前は、レッド・ソックスを語るに欠かせないだろう。2018年シーズン、8月初旬で2位ヤンキースに大差をつけて独走し、なんと108勝54敗という凄まじい勝率で勝ち抜いたことは、記憶に新しい。118年に及ぶ球団史上最高勝率で地区優勝を果たすと、破竹の勢いそのままにワールド・シリーズの頂点に立った。ナショナル・リーグの覇者ロサンジェルス・ドジャーズを寄せ付けない、圧倒的な強さを誇ったものだ。
だが球団には、そんな輝かしい戦歴ばかりでなく、むしろ語ることさえ憚りたくなる後ろめたい歴史があった。そもそも1919年シーズンを最後に、経営難に苦しむ球団は、ベーブ・ルースをヤンキースへと放出せざるを得なくなってしまう。案の定、翌20年シーズン以降の、ヤンキースとレッド・ソックスのアメリカン・リーグでの立場が逆転する。一方は、優勝戦線に絶えず名を残す最強チームに変貌し、他方は毎年のごとく低迷し続けるチームへと零落れてしまうのだ。誰が名付けたか、人はそれを「バンビーノの呪」と称した。「バンビーノ」とは、ベーブ・ルースの愛称だ。ルースを放出したレッド・ソックスが、その後ワールド・シリーズ制覇に手が届かなくなってしまうことを、皮肉るものだった。その「呪」は、なんと86年もの長きにわたって囁かれることになる。
ハワード・ブライアントの『シャット・アウト』(2002) は、いわばレッド・ソックスがその「呪」に藻掻き苦しみ、いかにしてそれを解きほどくに至ったのかを、明らかにする試みだった。1933年にトム・ヨーキーが球団を買収し、以来経営陣のトップとして君臨した40数年間に、一体何があったのか。著者は、球団史の生き証人として、過去・現在の経営陣から監督及び選手、報道関係者に至るまで、その数優に100名を越える人々へのインタヴューを試み、1册の著書にまとめ上げた。
タイトルの「シャット・アウト」には、2つの意味が込められている。ひとつは、言うまでもなく「投手が相手チームを完璧に封じる」というベースボール用語。そして、もうひとつが、本書の主要テーマである「(黒人をメジャー球界から)締め出す」という人種隔離政策のことだ。レッド・ソックスがメジャー球団の中で最後まで黒人選手を「締め出して」いたチームだ、と知る日本人は少ないだろう。もっとも、メジャー初の黒人リーガーがジャッキー・ロビンソンであり、彼を受け入れたチームがブルックリン・ドジャーズ(現ロサンジェルス)であることを知らない人はまずいない。ロビンソンに白羽の矢が立てられた経緯や、デビューを果たしたジャッキーの苦労話や、その活躍ぶりは、数々の書籍で紹介されたり、映画化されたりしている。中学・高等学校の英語の教科書にもたびたび登場しているほどだ。
副題が「レッド・ソックスに入団した黒人選手たちの物語」とあり、第1章では球団初の黒人パンプシー・グリーンが「トップ・バッター」として登場する。1959年のことだ。球団初とは言うものの「ジャッキー・ロビンソンのデビューに遅れること12年目」などと、絶えずロビンソン、あるいはウィリー・メイズとの対比が繰り返される。残念ながら、彼は、そんな比較には値しない、無名の新人選手に過ぎなかった。1950年代のメジャー球界はと言えば、すでに有色人種排除の方針が緩み、ジャッキー・ロビンソンを皮切りに、各チームは優れた黒人選手に触手を伸ばし、チーム力強化を図っていた。その最たる例が、ニューヨーク・ヤンキースだった。それに対し、その流れに乗れなかった、いや乗ろうとしなかったのが、ボストン・レッド・ソックスだったのだ。伝統あるチームであったがゆえに、オーナーのトム・ヨーキー始め球団経営陣にしてみれば、あえて白人優先の「紳士協定」を貫いただけだったのかもしれない。その結果、優勝からは見放される低迷ぶりに、辛酸を嘗めざるを得ない状態になっていたのだ。 ロビンソンやメイズの名が繰り返されるたびに、レッド・ソックスが一体どこでチーム力強化の路線を取り違えたのかと、ボストン生まれの著者の積年の思いが聞こえてくる。
読み進むと、すぐに状況が判ってくる。実は、ロビンソン獲得の機会が、メジャー球団のどこよりも早くレッド・ソックスにあった、という驚くべき真実が浮上してくる。ドジャーズのブランチ・リッキーが彼に目をつけるよりも早い段階で、球団は入団テスト(トライ・アウト)を施していたのだ。1945年4月というから、ロビンソンのメジャー・デビューの2年前のこと。ボストン市議会議員イザドア・マチニックと黒人スポーツ記者ウエンデル・スミスとによる画策が、背後にあった。スポーツ界での人種隔離(カラー・ライン)を撤廃しようと、球団に働きかけていたのだ。球団は、興行収入が高い日曜日の試合開催を天秤に架けられ、トライアウト実施にかたちだけでも、応じざるを得なかった。その段階で、球団経営陣に黒人選手を受け入れる意図など、もとよりなかったのは言うまでもない。
さらにその4年後、後にメジャー球界では「史上最高の中堅手」と評価される若きウィリー・メイズ獲得に向けて、球団は動いた。だが、テキサス出身のスカウトの勝手な判断で、メイズには接触すらしないという大失態を演じていたのだ。40年代に、この二人の黒人スーパースターを獲得していたら、レッド・ソックスに「バンビーノの呪」などというジンクスなど、まとわりつくはずもなかったというのが、著者の思いだったのだろう。
1959年春キャンプから、チームに招聘されたグリーンだった。だがチームの雰囲気は、自分が望まれた存在ではないことを物語っていた。すでに勝利の女神からは見放されていたチーム状況だったのに、新進気鋭の黒人選手の登場を待ちに待ったと期待した者はほとんどいなかった。他チームでは、すでに大活躍をして喝采を浴びる黒人選手の例は少なくなかった、というのに。
その原因を探るべく著者は、ボストンという街の歴史を繙く。かつて合衆国が奴隷制度下にあった当時から、奴隷制反対の声を上げた旗頭がボストンだったのに、街は複雑な歴史的環境に雁字搦めになっていたことが明らかにされる。南北戦争後、国内外から北部大都市への移民の流入はどこも似通った様相だったのだろうが、特にボストンでは、それぞれの地区でそれぞれの民族がひしめき合い、他民族への敵愾心が激しかったという。とりわけ有色人種への憎悪は辛辣だった。レッド・ソックス球団がようやく黒人選手獲得に腰を上げたのは、公立学校の差別撤廃を始めとして、公民権運動が大きなうねり声を上げようとしていた頃だった。そんな中、ボストン市街では、ひとつの対立が起こると、より激しい新たな対立を呼び起こす暴動の連鎖が90年前後まで止まなかった。フェアプレー精神の象徴的スポーツであるはずのベースボール界でも、公然と罷り通っていた黒人廃絶が取っ払われたとはいえ、グラウンドに立った黒人選手への激しい野次や侮蔑的な発言は最悪だったという。メジャー第1号として目覚ましい活躍をしたロビンソンも、ボストンでのプレーには二の足を踏んでいた。 その彼が、上述のユダヤ系市議会議員との個人的な交流を通して、現役引退後には公民権運動にのめり込んでいったのも自然の流れだったのだ。
そんな街にあった古豪球団が黒人の有力選手獲得に積極的になるのも、時代の流れだった。グリーンを受け入れたことで、クラブハウス内の「相部屋要員」として、黒人投手のアール・ウィルソンが同時に登用された。制球に難があったとはいえ、球団とすればグリーン以上の働きをしたウィルソンには、ほくそ笑んだものだ。60年代には、後に読売ジャイアンツの大物「助っ人」として来日するレジー・スミスの若き姿があった。67年の「奇跡のリーグ優勝」は、彼の左右の打席から繰り出された一試合二本の本塁打でなし得た、とも言われている。70年代になるとルイス・ティアント、トミー・ハーパー、ジム・ライス。さらにオイル・カン・ボイドにエリス・バークスが続く80年代。90年代には、ボストン人が待ちに待った生粋のニューイングランド人、モー・ヴォーンの登場があった。それぞれが、それぞれの時代の流れに翻弄されつつ、ベースボールと格闘する姿が活写されている。
春のキャンプ地で、あるトラブルに巻き込まれたアール・ウィルソンは、球団からは守ってもらえず、むしろ冷たくあしらわれた挙げ句、チームから放出されてしまった。相変わらず、白人優越主義がまかり通る南部フロリダ州での、些細な人種差別が原因だった。階級闘争と人種差別が蔓延る東海岸の街に、いつまでも馴染めなかった西海岸出身のスミス。球団からの差別待遇にことごとく怒りをぶちまけたから、トラブル・メーカーとされたものだ。ヘルメットを冠ったまま左翼の守備についた彼のトレード・マークは、ファンから投げ込まれる投石などから身を守る手段だった。変わらぬ球団体質に我慢しきれず、遂には訴訟沙汰を引き起こしたハーパー。ひたすらベースボールにのめり込み、生涯をレッド・ソックスで孤軍奮闘したジム・ライス。その彼に可愛がられた新人のエリス・バークスは、ライスとともに88年の地区優勝に貢献した。91年に登場した大型新人のモー・ヴォーンは、ニューイングランド期待の星だった。95年には、ワールド・シリーズこそ逃したが、シーズンMVPに輝く活躍をした。
もちろん、球団の体質が改善されるには、経営陣の刷新が不可欠だった。すでに60年代半ばから、古豪復活を目指して、人種の壁を越える人材確保に奔走したディック・オコネルの存在が大きい。だが、76年に球団トップのトム・ヨーキーが亡くなると、球団内クーデターが出来し、GMの座を追われてしまう。案の定、チームは再び低迷し出す。それを建て直したのが、80年代のルー・ゴーマン、90年代のダン・ドゥケットだった。ロジャー・クレメンス、ペドロ・マルティネス、マニー・ラミレスら大物選手の獲得は、各GMの積極的な尽力があったからこその賜物だ。そして2004年、遂にあの「呪」を解く復活劇が起きる。実に86年ぶりのワールド・シリーズ制覇だった。
「呪」を解いてからのレッド・ソックスの勢いは、今さら繰り返すまでもない。その選手層も、白人系はもとより、アフリカ系、ドミニカ共和国、キューバ、ヴェネズエラなどなど、実に多種多彩な顔ぶれになっている。もはやメジャー・リーグに「人種の壁」など存在しない、新しい時代になっていた。それこそ毎日のように、日本人プレーヤーの活躍ぶりが聞こえてくる。大谷翔平の二刀流が、あのベーブ・ルースに並んだとか、エンジェルズ戦の実況担当のビクター・ロハスによる「ビッグフライ、オオタニサン」が「名台詞」になっているのだ。そんな時代だからこそ、わずか半世紀前の出来事として、レッド・ソックスのみならずメジャー球界が、黒人選手を受け入れるか否かで、大揺れに揺れた時代があったことを記憶に留めおくことは意義深い。
その意味では、ハワード・ブライアントがなした業績は大きい。ベースボールがテーマとはいえ、日本人には馴染みの薄い合衆国の暗黒の歴史に、灯を点すものとなっている。合衆国建国精神の源と思われていた東海岸の街で、フェアプレー精神の象徴的スポーツ界で、理想とは裏腹な現実を生き抜かねばならなかった人たちの姿を、鮮やかに描き出してくれた。考えてみれば、厳しい「カラー・ライン」を打ち破りメジャー界で闘った黒人選手は、ジャッキー・ロビンソンだけではなかったはず。今回、レッド・ソックスの歴史を繙いてくれた著者のおかげで、数多くの黒人選手たちが日の目を見る機会になったことであろう。最後に、単なる歴史的記述に留まることなく、著者が織り込んでくれたいくつかの感動的な物語を紹介して、締めくくることとする。
その一つが、レッド・ソックス初の黒人選手パンプシー・グリーンと、バスケットボール界の黒人スーパースターとの交友関係だ。MLBに倣い、NBA合衆国バスケットボール・リーグも、すでに1950年にボストン・セルティックスがチャック・クーパーを入団させて以来、黒人選手の活躍が目覚ましくなっていた。56年メルボルン・オリンピックでの金メダルを手土産に、セルテイックスに入団したビル・ラッセルは、50年代末にはチームを8連覇へと導く大活躍で、NBA史上最高選手になっていた。そのラッセルが、自家用車にグリーンを乗せ、ボストン市内を連れ回す。市内各地区に存在する差別環境へと引っ張り出し、現実を教え諭すのだった。各民族・人種ごとに厳しく区割りされる中で、相互に関わり合う事もなく犇めく状況を「人種差別のフリーマーケット」と称しながら、そんな中でいかに生きて行くかの術を教示していくシーンは読み応えがある。もっともチーム内で右往左往していた新人グリーンをサポートしたのが、メジャー史上最高の左翼手として誉れ高い、かのテッド・ウィリアムズだった。試合前のウォーム・アップに、率先してグリーンをグラウンドに誘い出していた。 後年、殿堂入りを果たした際のスピーチで、ニグロ・リーグの英雄たちの殿堂入りを訴えたウィリアムズの発言は、世間を驚かすものだった。「黒いベーブ・ルース」と呼ばれたジョシュ・ギブソンと、史上最高の投手としてのサチェル・ペイジの実績を、正当に評価すべきだと。未確認記録ながら、前者はキャリア通算で972の本塁打を放ち、後者は通算2000勝を挙げたことが語りぐさとなっている人物だ。グリーンには、ウィリアムズがますますベースボール人として尊敬に値する人物と映ったに違いない。
二つ目は、すでに触れたジャッキー・ロビンソンと、ユダヤ系市議会議員イザドア・マチニックとの家族ぐるみの交友関係だ。ボストンで試合がある度に、マチニック家を定宿としていたという。後にロビンソンが、公民権活動家として歩み出す切っ掛けに繋がる。
そして三つ目が、チーム内で孤軍奮闘していたジム・ライスと、新人エリス・バークスとの間に生まれた、いわば子弟関係ともいえる関係だ。チームメイトとほとんど口を交わすこともなかったライスだったが、バークスには珍しくも進んでメジャー界でのイロハを教え込むのだった。それは、その直前に球団を訴えたことでチームを追い出された元同僚、トミー・ハーパーへの罪滅ぼしだったのかも知れない。そろそろ自身の体力の限界を感じ出していたライスには、若かりし頃の自分と、バークスの境遇とに接点でも見出したのか、ロッカーを自分の隣にするよう球団に頼み込んだり、ラッセルがグリーンにしたように、ボストンの街を連れ歩くという熱の入れようだった。そんな彼から「6年辛抱したら、ボストンなど、おさらばすりゃいいんだから」と言われたバークスの驚きは、如何ほどであっただろうか。
ちょうどこの本が発刊されたのは、日本のプロ野球界から合衆国のメジャー球界へと、海を越えて行く選手が続出していた頃だった。すでに野茂英雄はそのパイオニア的存在だったし、イチローは言うまでもなく、松井秀喜もこの頃に太平洋を渡っている。そのメジャー球界では、黒人差別という「カラー・ライン」を打ち破ったジャッキー・ロビンソンのデビュー50周年を祝して(1997年4月15日)、彼の背番号「42」がメジャー界全体の「永久欠番」にされていた。その後2004年には、4月15日が「ジャッキー・ロビンソン・デイ」に制定され、今では毎年この日に全選手が背番号「42」のユニフォームを着用して試合に臨むのが慣例となった。
おそらく、そんな折に発行された書籍だったから、目に留まったのだろう。メジャー入りしたロビンソンの孤軍奮闘ぶりは、すでに昔語りになりかかっていたし、ベーブ・ルースの本塁打記録を打ち破ろうとしていたハンク・アーロンへの嫌がらせも、過去の出来事だった。通算本塁打記録を達成するバリー・ボンズが全盛であり、アレックス・ロドリゲスやサミー・ソーサーらのドミニカ共和国勢が次から次へと頭角を現していた頃だ。そこにトルネード投法の野茂や、シーズン最多安打を放つイチローら日本勢が参入するという、まさにメジャー界は多種多彩の選手が活躍できる場になっていた。そんな折に、メジャー球界で「カラー・ライン」を最後まで堅持したレッド・ソックス球団の真実を暴露する書籍の発刊だったのだ。
< 原 典 > Howard Bryant 著
"SHUT OUT"( 2002 ) ISBN0807009792
A Story of Race and Baseball in Boston